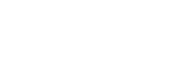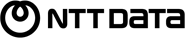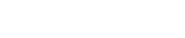ERPとは
ERPと支出管理クラウドの違いや対象となる業務について紹介します。
ERP(Enterprise Resource Planning:企業資源計画)とは
ERPとは、企業が持つ経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報)を有効活用し、経営の効率化を図るための統合的なシステムです。
ERPの役割
企業は、事業活動を行う上で様々な情報を管理する必要があります。
例えば、顧客情報、販売情報、在庫情報、会計情報、人事情報など、これらの情報は部門ごとに管理されていることが多く、情報共有や連携がスムーズに行かない場合があります。
ERPは、これらの情報を一元的に管理し、各部門間で共有・連携できるようにすることで、業務効率化や経営判断の迅速化に貢献します。
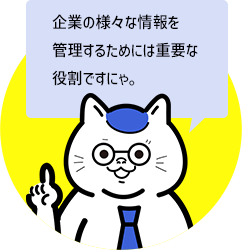
ERPのメリット
ERPを導入することで、企業は以下のようなメリットを得られます。
-
Merit01
業務効率化
各部門の情報を一元管理することで、情報共有や連携がスムーズになり、業務プロセスを効率化できます。
-
Merit02
コスト削減
業務効率化により、人件費や管理費などのコストを削減できます。
-
Merit03
経営判断の迅速化
リアルタイムに経営情報を把握できるため、迅速な意思決定が可能になります。
-
Merit04
顧客満足度向上
顧客情報を一元管理することで、顧客ニーズに合ったサービスを提供できるようになり、顧客満足度向上に繋がります。
-
Merit05
競争力強化
業務効率化や経営判断の迅速化により、競争力を強化できます。
ERPの種類
ERPには、様々な種類があります。
-

基幹業務システム
企業の基幹業務(会計、人事、販売、購買、在庫管理など)を統合的に管理するシステムです。
-
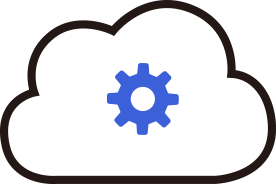
クラウドERP
クラウド上で提供されるERPシステムです。
-

業種別ERP
特定の業種に特化したERPシステムです。
ERPの対応範囲
ERPシステムの対象業務
Slopebase
対象範囲外
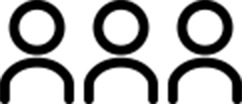
財務・管理会計
(電子帳簿保存法)
HCM(人事/給与/勤怠/労務)
Slopebase対象範囲
-

予算管理
予算・売上・原価
-

資産・リース管理
固定資産・リース
-

債権・債務管理
債権・債務・決済・入金
-

販売・購買管理
調達・受注・発注・請求・支払・契約
-

経費清算
経費・出張旅費・交通費
-

営業・顧客管理
仕入れ先・得意先・案件
-

在庫管理
商品・在庫
-

生産管理
生産計画・作業・工程・品質・設備
ポストモダンERP
ポストモダンERPとは、従来のERPの課題を克服し、企業の多様なニーズに対応できる次世代のERPの考え方です。
従来のERPは、単一のシステムで全ての業務を網羅しようとするため、以下の課題がありました。
- システムが複雑化し、柔軟性に欠ける
- 導入・運用コストが高い
- 最新のテクノロジーを取り入れにくい
一方、ポストモダンERPでは、コアとなる基幹業務に特化したERPを導入し、その他の業務はクラウドサービスやSaaS等の外部システムと連携させることで、
柔軟性、拡張性、コスト効率性を高めます。
ERPと支出管理クラウドの違い
支出管理クラウドはERPの範囲の内、販売管理、購買管理、在庫管理、生産管理に特化したシステムです。
コアとなる基幹業務は、専用のシステムを導入し、その他の業務に特化しています。
例えば、財務会計では、仕訳データを会計システムに連携します。
電子帳簿保存法の対応は、会計システム側で行います。
人事管理では、人事管理に特化したシステムを個別に導入することで、ERPの対応範囲と同等の範囲に対応できます。

支出管理クラウドでできること

ERPは、企業経営を効率化するための強力なツールです。
ERP導入を検討する際には、自社の課題やニーズを明確にし、最適なERP製品を選択することが重要です。
このため、柔軟性、拡張性、コスト効率性のある製品でスモールスタートできると、スムーズに導入できます。
関連項目:ノーコードプラットフォームとは