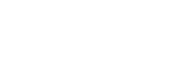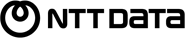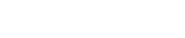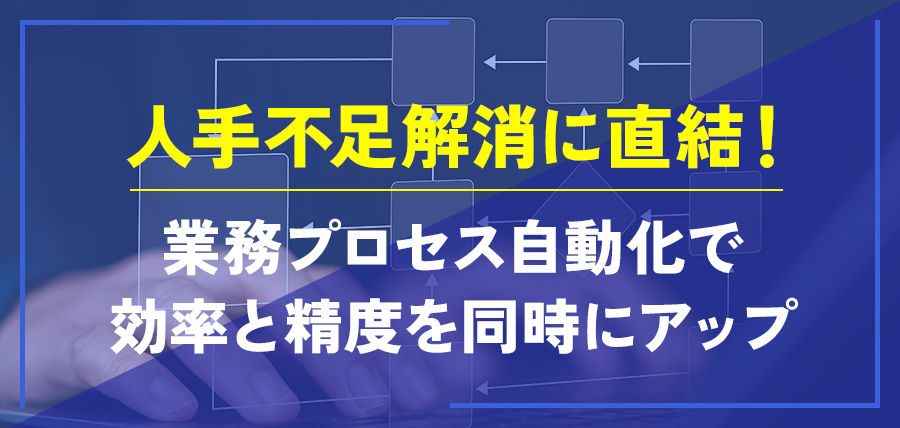04
AIロボティクスが可能にする「生産性向上」の具体策
AIロボティクスの導入は、人手不足を解消し、企業の生産性を飛躍的に向上させる原動力となります。
24時間稼働による生産量の最大化
AIロボットは、人間のような疲労や集中力の低下とは無縁であり、休憩やシフト交代を必要とせずに24時間365日の連続稼働が可能です。
特に、需要のピーク時や、グローバル市場からの短納期が求められる案件において、この能力は企業の受注機会を大きく広げる強力な武器となるでしょう。
AIによる高精度な作業と品質の安定化・向上
AI画像認識を用いた外観検査システムは、数ミクロン単位の微細な傷や欠陥、色むらなどを、熟練した人間の目でも見逃してしまうレベルで高速かつ高精度に検出します。
また、組み立てや溶接といった精密作業においても、AIロボットは常にプログラムされた通りの一定の品質を保ちます。
段取り替え時間の短縮
多品種少量生産において、生産性のボトルネックとなりがちなのが、生産品目を切り替える際の「段取り替え」に要する時間です。AI搭載のロボットシステムは、次に生産する製品の設計データ(CADデータなど)を読み込み、ロボットハンドの爪や治具、動作プログラムなどを自動で調整・変更することが可能です。
これにより、従来は数時間かかっていた段取り替えを数分単位に短縮し、生産ラインの停止時間を最小限に抑えることができます。
AGV/AMRによる工場内物流の最適化とリードタイム短縮
AGV(無人搬送車)や、より高度なAMR(自律走行搬送ロボット)は、工場内の物流を一変させます。
特に、AMRは、AIによって工場内の地図を自ら生成し、人や障害物をリアルタイムで回避しながら最適な経路を判断して走行するため、仕掛品在庫の圧縮や、生産リードタイムの短縮に大きく貢献します。
データ収集・分析による継続的な工程改善
AIロボットは作業を実行するだけでなく、その稼働データ、作業ログ、各種センサーから得られる情報といった膨大なデータをリアルタイムで収集・蓄積します。
これらのビッグデータをAIが分析することで、生産ライン全体のボトルネックとなっている工程の特定や、チョコ停(短時間の設備停止)の原因分析、さらには、モーターの振動や温度変化から故障の予兆を検知する「予知保全」などが可能になります。