01
固定資産台帳とは? - なぜ経理にとって「超」重要なのか?

固定資産台帳は、建物や設備など事業で使用する減価償却資産ごとに取得価額や償却状況を記録・管理する帳簿で、固定資産税の申告や財務諸表の作成にも欠かせません。
法人税法や地方税法などで作成・保存が義務付けられている帳簿書類に位置付けられ、不備があると税額の計算に影響が出るため、追徴課税や粉飾決算の疑義などにつながる恐れがあります。
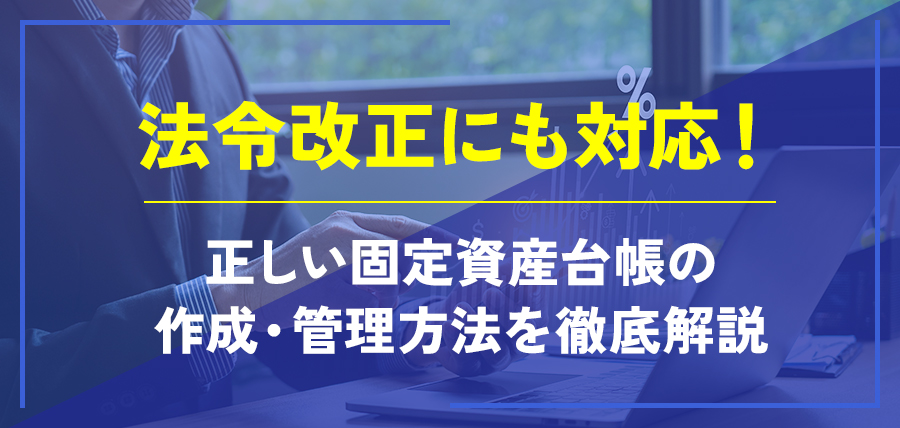
〈 トピックス 〉
01

固定資産台帳は、建物や設備など事業で使用する減価償却資産ごとに取得価額や償却状況を記録・管理する帳簿で、固定資産税の申告や財務諸表の作成にも欠かせません。
法人税法や地方税法などで作成・保存が義務付けられている帳簿書類に位置付けられ、不備があると税額の計算に影響が出るため、追徴課税や粉飾決算の疑義などにつながる恐れがあります。

TRIAL
02
実は、固定資産台帳には明確な記載ルールがありません。
ここでは、税務申告や会計処理を正しく行うために一般的に必要とされる記載項目を紹介します。
まず、資産の基本情報として以下の項目を記録しましょう。
次に、減価償却に関する項目は以下のとおりです。
続いて、資産の移動や処分に関する以下のような情報も記載します。
そのほか、固定資産台帳には以下の項目も記載するとよいでしょう。

TRIAL
03
ここからは固定資産台帳を新規作成する手順を紹介します。既存台帳を根本的に見直す際も、こちらの手順で進めましょう。
まずは、社内にある固定資産をもれなく洗い出します。
固定資産とは、一般的には「使用可能期間1年以上かつ取得価額10万円以上」の機械や備品などを指します。土地・建物・車両・備品など有形資産だけでなく、ソフトウエアといった無形資産も対象です。
固定資産の取得価額は、購入代金だけでなく運送費や設置費などの付随費用も含めて算定します。
また、取得価額に消費税を含めるか否かについては、事業者の経理方法により、税込経理なら含める、税抜経理では含めないこととなります。
固定資産の耐用年数は国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」を参考にします。 なお、中古資産については残りの使用可能期間を見積もって耐用年数としますが、見積もりが難しい場合には以下の式で算定しましょう。
その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数
償却方法は主に定額法と定率法の2種類があります。
また、取得価額が10万円未満かつ使用可能期間が1年未満の資産は経費(消耗品費)として処理します。
そのほか取得価額が10万円以上20万円未満の資産なら、耐用年数に関係なく3年で償却する方法も採用できます。
Step4までに決定した情報を、Excelや会計ソフトなど台帳として使うツールにもれなく入力していきましょう。管理番号をラベルにして各資産に貼っておくと、台帳と現物の照合や棚卸しがスムーズになります。

TRIAL
04

さて、ここからは固定資産台帳の管理にも影響を与える近年の法改正や制度変更などを紹介します。対応のポイントを押さえておきましょう。
固定資産台帳も電子帳簿保存法の対象で、モニター・説明書等の備付けやダウンロードへの応諾といった要件を満たせば電子保存が可能です。
インボイス制度の経過措置期間中(~2026年9月)に免税事業者から機械や備品を購入した場合、消費税額の80%相当額について仕入税額控除を適用できます。
中小企業投資促進税制や経営強化税制を利用するには、期日までに資産を「取得」するだけでなく「指定事業の用に供すること」が要件です。
2027年度から新リース会計基準が適用となり、該当企業は資産計上することとなるリース資産の範囲が拡大します。

TRIAL
05
固定資産台帳は作成して終わりではなく、常に最新かつ正確な状態の維持が重要です。ここでは、台帳を適切に管理するポイントを紹介します。
Excelでも関数や入力規則の活用により、計算の効率化やミスの防止を期待できます。ただし、資産の増加とともにシートの管理も煩雑になりがちです。
多くの会計ソフトには減価償却費を自動計算し、仕訳まで連動させる便利な機能が備わっており、固定資産税の申告書作成もよりスムーズになるでしょう。
資産数が多い企業や、バーコード等を使った現物管理との連携、複雑なリース資産の管理が必要な場合は、固定資産管理に特化したシステムの導入が効果的です。 会計ソフトでは対応しきれない現物管理や棚卸しの効率化を期待できます。
固定資産台帳の記載情報と実際の資産が一致しているか、最低でも年に1回は棚卸しをして確認しましょう。

TRIAL
06
ここでは、とくに中小企業の経理担当者が抱きがちな疑問にQ&A形式でお答えします。台帳を適切に運営する参考としてください。
取得価額が10万円未満の備品は、減価償却ではなく、購入した年度に全額を経費(損金)として処理します。固定資産台帳には原則記載不要ですが、社内管理上は一覧表などで記録しておくと安心です。
先述のとおり、中古資産については残りの使用可能期間を見積もって耐用年数としますが、見積もりが難しい場合には以下の「簡便法」にて算定します。
バージョンアップによって新機能の追加や性能の向上があった場合、バージョンアップ費用は固定資産の取得価額に加算します。
一方、バージョンアップが障害の除去や現状維持にとどまる内容なら、修繕費として当期の経費に計上しましょう。
除却や売却にともなう会計処理を適切に行ったうえ、固定資産台帳で該当資産を除売却済みのステータスにしましょう。このとき、処分の事実と日付がわかる記録(書類など)を残しておくと、損金経理の根拠として安心です。
耐用年数を過ぎて減価償却が終わった資産は、帳簿上の価値がなくなっただけであり、引き続き使用しても問題ありません。ただし、台帳から削除はせず、適切な管理を継続しましょう。また修繕費や維持費は今後も経費として処理できます。

TRIAL
07

TRIAL
08
バックオフィス業務の
支出管理を支援する、
支出管理クラウド

※バックオフィス業務とは経理や総務、人事、法務、財務などといった直接顧客と対峙することの無い社内向け業務全般を行う職種や業務のこと

TRIAL
この記事を書いた人

早稲田大学卒業後、関東信越国税局採用。税務大学校を首席卒業(金時計)し、税務署法人課税部門にて法人税、消費税等の税務調査に従事。複雑困難事案の事績により署長顕彰。大手監査法人に転職後、製造業や不動産業をはじめ様々な業種の上場会社監査やIPO監査に従事。その後、中央官庁勤務を経て大手証券会社の引受審査部・公開引受部にてIPO業務に従事。現在は主に法人の税務顧問を務めており、スタートアップ支援に強みを有する。