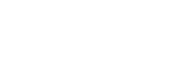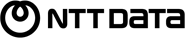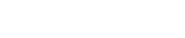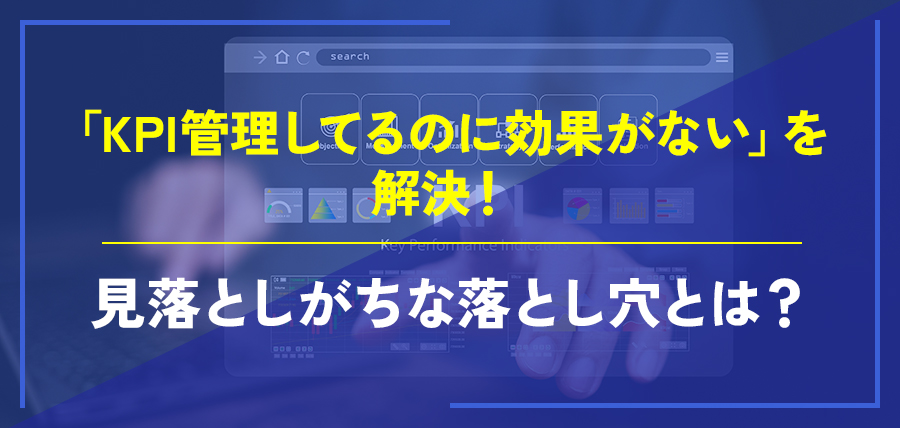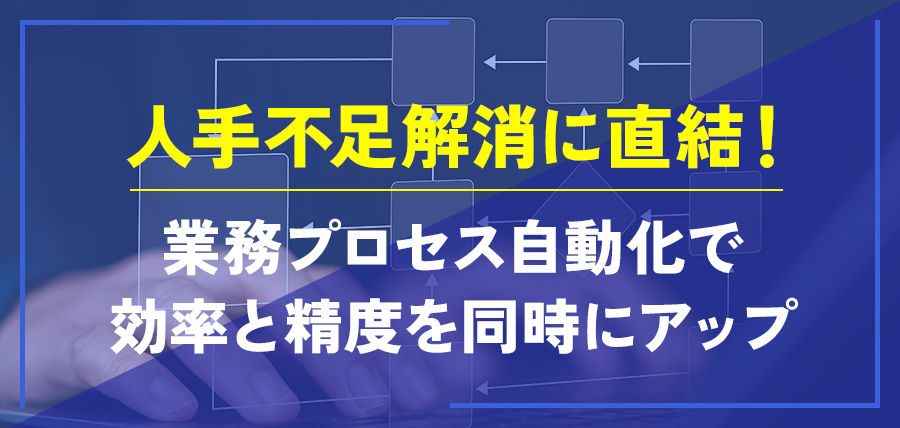01
なぜKPI管理は失敗するのか?効果が出ない7つの「落とし穴」

KPI管理がうまくいかない理由は多岐にわたりますが、多くの組織で共通して発生する失敗のパターンがあります。ここでは、特に陥りやすい7つの落とし穴について、具体的な事例と共に解説します。
落とし穴1:【目的とのズレ】KGIとKPIの連動性が低く、何のためのKPIか不明確
本末転倒とも言える失敗が、KPI管理における本来の目的であるKGI(重要目標達成指標)との連動性を見失ってしまうことです。
具体的な失敗例を挙げましょう。ある大手企業では、メール広告の「開封率」をKPIに設定しました。その結果、件名に過度な煽りや過剰な訴求が入ったメールを送るようになってしまいました。
開封率の数字だけを追った結果、「開封さえされれば良し」という考えに陥り、顧客体験を損ねることは全く考えずに、手段を選ばなくなったのです。KPIは向上したものの、ブランド信頼は下がり、最終的な売上目標(KGI)には貢献しないという本末転倒な状況が生じました。
ここから学べる教訓に「グッドハートの法則」があります。これは「測定指標が目標になると指標として機能しなくなる」というもので、まさにKPIが目的とズレた状態を指しています。
落とし穴2:【指標の曖昧さ】KPIの定義が曖昧、または測定・計測が困難
KPIは、具体的かつ数値で測定できるものであるべきですが、現場感覚の乏しい設計により「曖昧な指標」をKPIにしてしまうケースがあります。例えば「品質意識を高める」「安全に配慮する」「顧客満足度向上」といった一見重要そうな目標も、定量化されていなければ人によって解釈が異なり、評価も改善もできません。
この落とし穴を回避するためには、SMARTの法則に沿ったKPI設定が効果的でしょう。
SMARTは、目標設定を効果的に行うためのフレームワークで、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性)、Time-bound(期限付き)の5つの要素の頭文字を組み合わせたものです。この法則を用いることで、目標がより明確になり、達成しやすくなるとされています。
落とし穴3:【多すぎる・少なすぎる】KPIの数が不適切で焦点がぼやける、または重要な観点が漏れる
「あれもこれも管理しよう」と欲張るあまり、KPIを過剰に設定してしまう落とし穴です。人間心理として「数字で管理すれば安心」という発想がありますが、何でもかんでも数値化しようとするとかえって焦点がぼやけます。1つの部門に5~6個ものKPIを課せば、現場は「結局何を優先すればいいのか分からない」という状態に陥ります。
本当に重要な指標は何かを意識し、定期的に見直しを行い、「Keyではない指標はKPIから外す勇気」を持つことが組織には必要です。
落とし穴4:【目標値の問題】目標値(基準値)の設定が不適切(低すぎる・高すぎる・根拠がない)
KPI自体は適切でも、その目標値(ターゲット)の設定を誤ることで、落とし穴に陥るケースです。特に多いのが、現実離れした高すぎる目標です。「高い目標を掲げればやる気が出るだろう」という経営側の心理から起こりがちですが、度を越すと逆効果になります。
この落とし穴を象徴する例が、米国ウェルズ・ファーゴ銀行の不正口座開設スキャンダルです。同銀行では「1人の顧客に8つの口座を持たせる」という過剰な販売ノルマ(KPI)が課され、従業員は、その厳しいノルマを達成するために顧客に無断で口座やクレジットカードを開設する不正行為に走りました。最終的に数千人の行員が処分され、巨額の制裁金を支払う事態となりました。
適切な目標を設定するため、過去実績や業界ベンチマークを参考に、実現可能な範囲を見極めましょう。
落とし穴5:【アクション不在】KPI数値を「見るだけ」で終わり、具体的な改善行動に繋がっていない
KPIを設定しただけで満足してしまい、その後のアクションやフォローが伴わないケースです。経営陣はKPIを決めたことで仕事をした気になりがちですが、現場への周知や実行計画づくりが不十分だと、KPIは絵に描いた餅になります。
とある企業では、「3か月前にKPIを決めたけど、今どうなっているか誰も知らない」という状況に陥りました。KPI設定後、一度も進捗確認の場を設けず放置していたため、現場メンバーは、目標値すら忘れて日常業務に追われていたのです。また別の例では、KPIを定めたものの責任者が曖昧で「結局誰が動くのか」が決まっておらず、誰も主体的に動かなかったために何ひとつ改善されなかったというケースもあります。
KPIは設定がスタートであり、運用が最も重要です。決めただけで終わることを防ぐには、以下のタスクが不可欠です
・グラフなどで見える化した数字をもとに「次の一手」を議論し共有する
・KPIごとに責任者を明確に定める
・未達時のリカバリープランを事前に用意しておく
落とし穴6:【現場との乖離】現場メンバーへのKPIの意図・重要性が浸透しておらず、「やらされ感」が蔓延
KPI設定に現場の声を反映しないと、経営層の考える指標と現場の実態にギャップが生まれます。上から一方的に与えられたKPIに対して、現場は「やらされているだけ」と感じ主体性が育ちません。特に、そのKPIが日々の業務と関連性が薄かったり、現場の数値感覚とかけ離れていると、メンバーは自分事として捉えられず関心を持てなくなります。
現場との乖離を防ぐためには、「現場主導で考える」ことが大切です。現場の納得感がない目標は机上の空論に過ぎず、いわばピントの合っていないメガネのようなものです。
落とし穴7:【硬直化】一度設定したKPIを状況変化に合わせて見直さない
KPIの硬直化とは、状況変化に対応せず指標を固定化してしまうことです。組織には、一度決めた指標を惰性で守り続ける傾向があり、「せっかく時間とコストをかけて作ったKPIだから」「過去から続けているから」という心理で不要なKPIを抱え込むことがあります。
あるEC企業では、利用者がスマホアプリ主体に移行した後もウェブサイトのKPIばかり追っていたため、現場から「指標を達成しても肝心の事業成長に結びつかない」と指摘されました。KPI達成率は高くてもアプリユーザー満足度は改善しないというミスマッチが発生したのです。