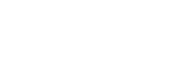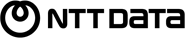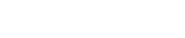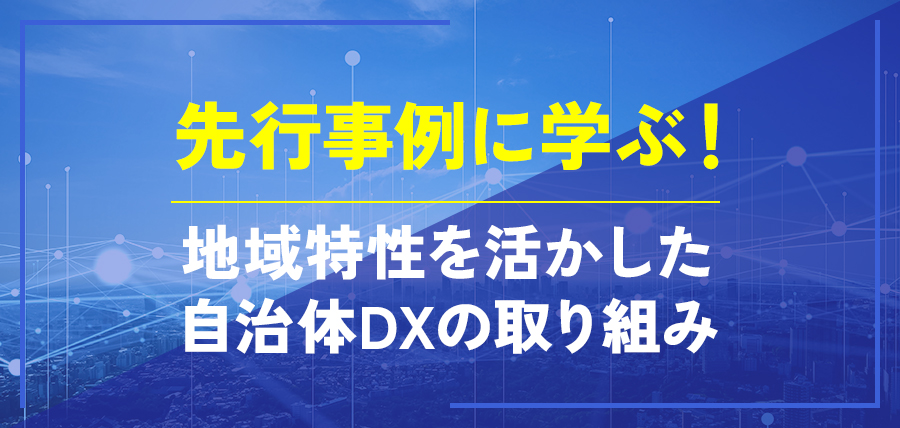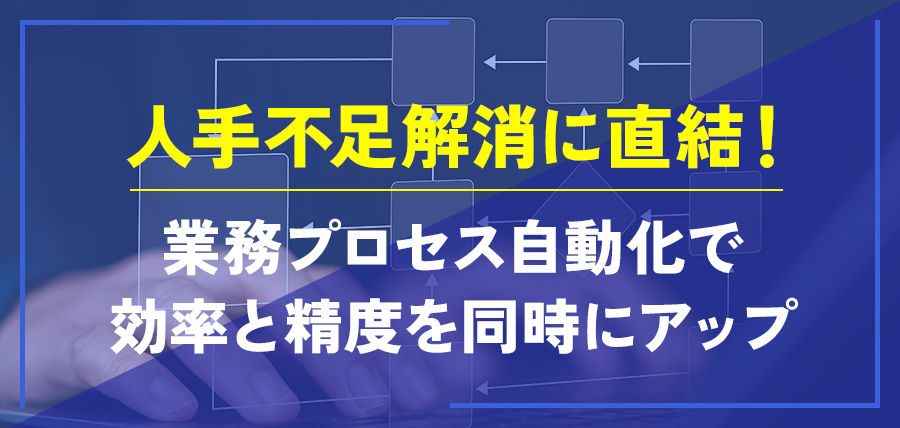04
我が自治体でDXを成功させるための5ステップ
先行事例から見えてくるのは、DXの成功が単一の要因によってもたらされるものではないという教訓です。首長のリーダーシップ、職員の意識、適切な技術選定、そして住民や事業者との協働など、複数の要素が有機的に連携することで成功につながります。ここでは、管理職が主導してDXを成功に導くための具体的な5つのステップを解説します。
Step1: 地域課題の棚卸しとDXビジョンの明確化
DX推進の第一歩は、自らの地域を客観的に知ることから始まります。人口動態や産業構造、財政状況などの統計データや、住民アンケートの結果などを基に、地域の現状と課題を徹底的に「棚卸し」しましょう。
課題が明確になったら、次に「DXによって、この地域を5年後、10年後にどのような姿にしたいのか」というビジョンを策定します。このビジョンは、単に「業務を効率化する」といった抽象的なものではなく、「オンライン手続きの利用率を〇〇%向上させ、窓口の待ち時間を平均〇分短縮する」といった、具体的で測定可能な目標(KPI)を伴うべきです。
明確なビジョンとKPIがあって初めて、DXは組織全体の羅針盤となり得ます。
Step2: 推進体制の構築と「巻き込み力」
DXは、情報システム部門だけの仕事ではありません。全庁を挙げて取り組むべき経営改革であり、その推進には強力な体制が不可欠です。
総務省の「自治体DX推進計画」でも、首長の強いコミットメントのもと、副市町村長などをCIO(最高情報責任者)に据え、全庁横断的な推進体制を構築することが推奨されています。
しかし、役職者を任命するだけでは組織は動きません。ここで管理職に求められるのが「巻き込み力」です。
・職員に対して:DXのビジョンを丁寧に共有して当事者意識を醸成し、各部署の推進リーダー選出や若手の意見登用を進める。
・住民に対して:ワークショップや意見交換会を通じて計画段階から参画を促し、本当に求められるサービスは何かを共に考える。
・地域事業者に対して:地元のIT企業等と連携して新サービスの共同開発や実証実験を行い、DX推進と地域経済の活性化を両立させる
職員、住民、事業者をDX推進の当事者として、巻き込んでいきましょう。
Step3: スモールスタートとアジャイルな改善
最初から全庁規模で大規模なシステムを導入しようとすると、莫大なコストと時間がかかるだけでなく、失敗したときのリスクも大きくなります。
まずは、成果が出やすく、かつ多くの職員や住民が効果を実感しやすい特定の分野に絞って小さく始めてみましょう。これをPoC(概念実証)と呼びます。
PoCを通じて、導入したツールの有効性や課題を検証し、利用者からのフィードバックを基に、改善を繰り返します。
そうしてPDCAを回していくことで、リスクを最小限に抑えながら、現場のニーズに合った実用的なシステムを着実に育てていきます。
小さな成功体験の積み重ねは、職員の自信につながりますし、さらなるDXへの機運も醸成されるでしょう。
Step4: データ利活用基盤の整備とセキュリティ確保
DXを推進していくと、庁内の様々な部署やシステムにデータが蓄積されていきます。これらのデータを部署の壁を越えて連携・分析し、政策立案や住民サービス向上に活かすための仕組みを整備していきます。
その際の選択肢として、国は「ガバメントクラウド」を提供しています。これは政府共通のクラウドサービス利用環境で、自治体が個別にシステムを構築・運用するコストを削減し、システムの標準化・共通化を促進することを目的としています。
一方で、データの利活用を進める上で絶対に疎かにしてはならないのが、個人情報保護とサイバーセキュリティの確保です。マイナンバーカードの活用拡大や行政手続きのオンライン化が進む中、住民のデータをいかに安全に守るかは、行政に対する信頼の根幹に関わる問題です。
常に、最新の脅威を想定したセキュリティ対策を徹底し、住民が安心してデジタルサービスを利用できる環境を整備することが、行政の責務といえます。
Step5: 継続的な人材育成とスキルアップ
DX推進の成否を最終的に左右するのは「人」です。しかし、多くの自治体でデジタル人材の不足が深刻な課題となっています。外部から専門家を登用することも有効な手段ですが、それと同時に、内部の職員を継続的にいく必要があります。
総務省やJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)では、自治体職員向けの多様な研修プログラムを提供しています。
こうした機会も積極的に活用し、組織全体のITスキルを継続的に高めていきます。