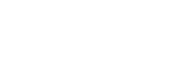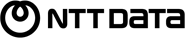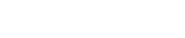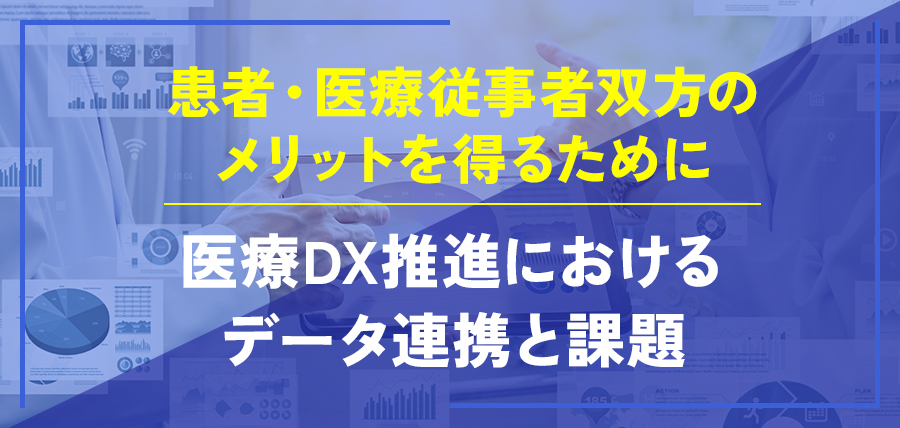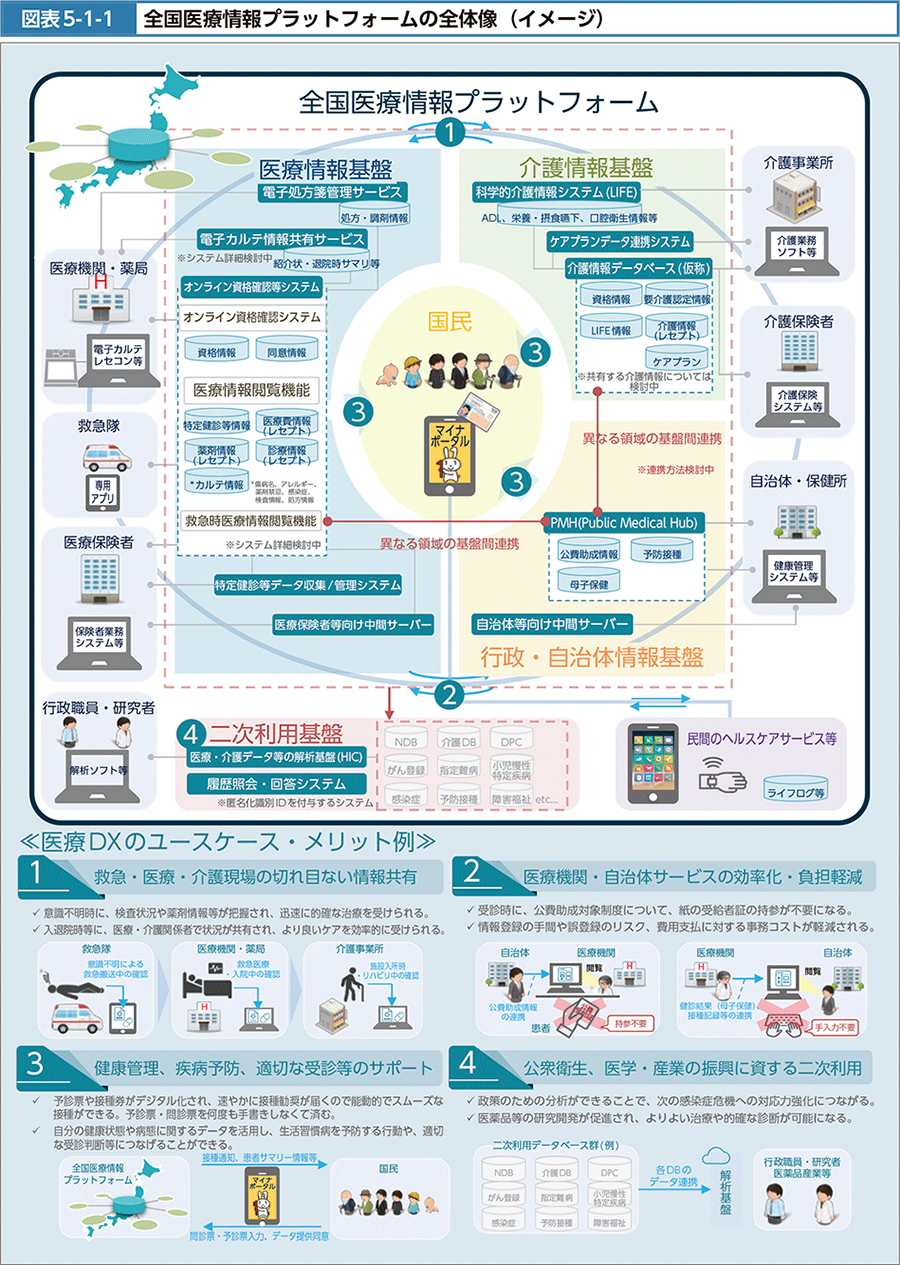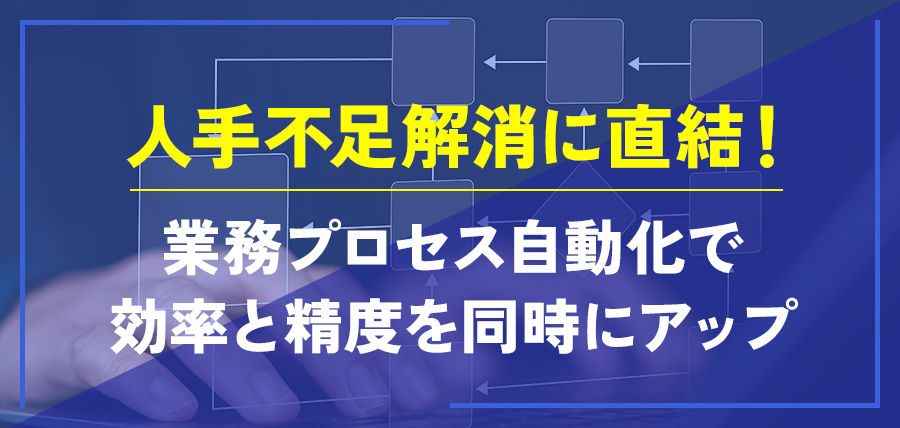03
現場を悩ます「データ連携」の壁 ~推進を阻む7つの課題~
より良い医療を実現する、また医療DXを実現するうえで、医療データの連携は重要です。しかし、現場では、連携がなかなか進まないケースも少なくありません。
データ連携の推進を阻む項目は、7つあります。どのような課題があるか、順に確認していきましょう。
課題1:システムの壁(ベンダーロックイン、標準規格の未導入・非互換)
データ連携は、システムそのものの壁に阻まれるケースもしばしばあります。以下のように、院内にサーバを置くオンプレミス型のシステムが使われているケースも多いでしょう。
・オーダーメイドのシステムを活用している
・パッケージシステムに対して、カスタマイズやアドオンを加えている
新しいシステムの導入は、既存システムとの連携が重視されます。他社で魅力的なシステムがあっても、稼動するシステムとベンダーを揃えなければならない「ベンダーロックイン」の壁に阻まれる場合もあります。高額な費用を余儀なくされる、または、導入を断念せざるを得なくなるかもしれません。
医療機関向けのシステムには、国際規格や厚生労働省が定めた標準規格があります。しかし、広く活用されている標準規格は「標準病名マスター」など一部に限られます。データ入力用の書式や、デジタル画像に関する項目の標準化も進んでいません。
データの書式が異なるシステムどうしの連携は新たなシステムの構築やツールの活用を要するため、データ連携のハードルとなります。
課題2:費用の壁(導入・改修コスト、費用対効果の不透明さ)
システムに関する費用も、データ連携を阻む大きな壁のひとつです。その費用は、しばしば数百万円から数千万円、またはそれ以上になる場合もあります。加えて、毎年の保守・運用費用も、悩みのひとつです。医療機関では、自院で価格を決められないものも多いため、利益の確保は簡単ではありません。このため、システムの導入や改修費用は簡単に捻出できません。
このような状況でシステムに関するプロジェクトを進めるためには、事前に費用対効果の保証を得ることが求められます。しかし、事前に十分な費用対効果を確認できるとは限りません。
「本当に導入して費用対効果を得られるか」という疑念を持つままの状態で、データ連携に踏み切ることは難しいかもしれません。
課題3:運用の壁(入力負担増、業務フロー変更への抵抗)
データ連携の実現には、システムの運用面における壁もあります。新たなシステムへの入力が必要、システムへ入力する項目が増えるといった負担の増加は、現場からの抵抗を招く場合もあります。
データ連携の導入により、業務フローが変わることへの抵抗も見逃せません。
運用の壁を越えるためには、業務軽減などのメリットを考えることが必要です。
課題4:セキュリティの壁(個人情報保護、サイバー攻撃リスク)
セキュリティの確保も、データ連携の壁となる項目です。医療機関が保有するデータには、個人情報が数多く含まれるため、高いセキュリティの確保が求められます。一方で、医療機関が保有する情報は、悪意ある者のターゲットとなりやすいことに留意が必要です。このため医療機関は、サイバー攻撃の標的となるリスクがあります。
データ連携の実現には、これらの課題をクリアしなければなりません。
暗号化などセキュリティに関する知識を学ぶ必要があることも、実現に向けた壁のひとつです。
課題5:制度・法律の壁(関連法規の複雑さ、責任の所在)
医療機関の業務は、多種多様な規制を受けています。例えば、個人情報保護法は、患者の大切な個人情報を守るうえで重要な法令です。データ連携の導入により、法令違反となる事態は、ぜひとも避けなければなりません。
一方で、法令の正確な理解は、簡単ではありません。法令によっては頻度高く改正されるものもありますから、変更に追随することも求められます。
課題6:人材の壁(ITスキル不足、データ活用人材の不在)
日本医師会では、2024年12月25日に公表した「診療所における医療DXに係る緊急調査 結果」において、全体の91.9%の医療機関でICTの知識を持つ人材が不足していることを示しています。64.1%の施設では、医師が診療の傍らシステム対応を行っている状況です。
このような状況では、データ連携の施策を打ち出しにくく、推進もしにくいでしょう。
出入りのITベンダーから提案がされない限り、データ連携のきっかけをつかめないかもしれません。
課題7:意識の壁(連携メリットへの理解不足、変化への不安)
人は「いつも通り」であることに安心感を持つ一方で、変化に対して漠然とした不安を感じがちです。データ連携への支持を得るためには、変化への不安を上回るメリットを提示することが求められます。
データ連携がもたらすメリットの理解が不足する状態では、「そもそも変える必要があるか?」と思われて、なかなかデータ連携への支持を得ることは難しいでしょう。