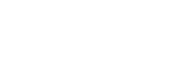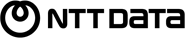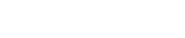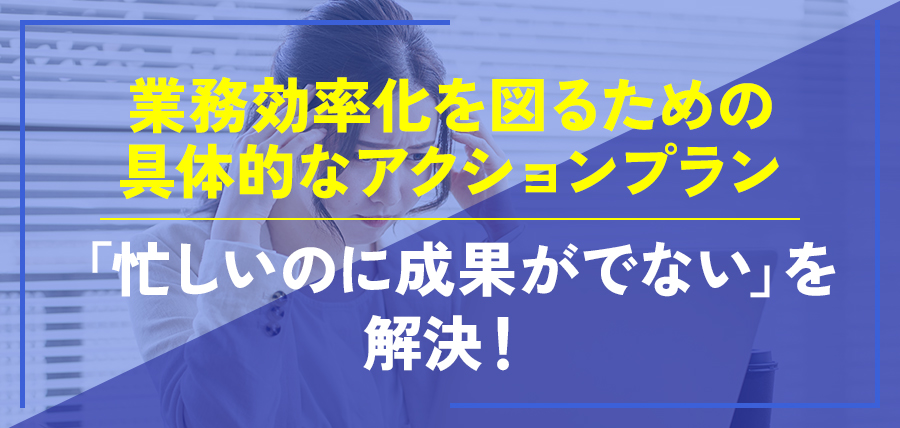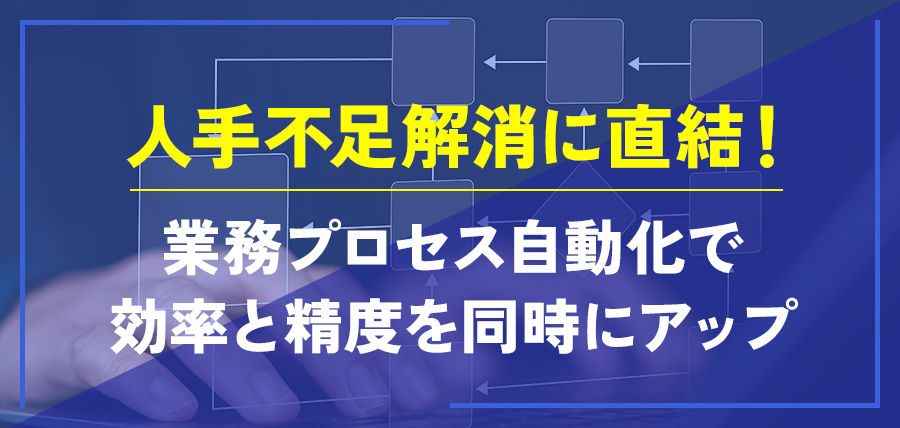02
業務効率化とは? - 時短が目的ではなく、成果創出がゴール
業務効率化の本質は、インプットとアウトプットのバランスを最適化することです。
この場合のインプットとは、業務に投入する時間、労働力、コストなどを指します。そしてアウトプットとは、業務によって生み出される成果物や付加価値です。つまり、業務効率化とは、より少ないインプットで、より大きなアウトプットを生み出すための活動と定義できます。
ここで重要なのは、インプットであるコストや時間の削減だけに目を奪われてはならない点です。
確かに、不要なコストを削減することは重要です。しかし、必要な投資まで削ってしまうと、顧客満足度の低下や社員の疲弊を招き、企業の競争力を損なうことになります。
業務効率化の目的は、単なる削減ではなく、創出にあります。付加価値の低いノンコア業務のインプットを減らし、それによって生み出された時間や人材、コストなどの貴重なリソースを、新商品開発や顧客への価値提供といった付加価値のあるコア業務に再投資することこそが、真の業務効率化です。
ここでは、この「価値の再配分」を適切に行うために、明日から実践可能な3つのステップから成る具体的なアクションプランを以下に紹介します。
STEP1:問題発見
STEP2:改善策立案
STEP3:実行と定着
【STEP1: 問題発見】あなたの部署の「ムダ」を見える化する
業務効率化の第一歩は、現状を正しく把握することから始まります。感覚的に非効率だと感じている部分を、客観的な事実として見える化することで、初めて的確な改善策を打つことが可能になります。
業務の洗い出しと分類 - 何にどれだけ時間を使っている?
まず、部署のメンバーがいつ、誰が、何を、どれくらいの時間を使って行っているのか、すべての業務をリストアップします。
次に、洗い出した業務を以下の2つに分類します。企業の利益に直結するコア業務と、それを遂行するために必要な付帯的・定型的なノンコア業務です。多くの場合、成果が出ない原因は、このノンコア業務に大半の時間を費やしていることにあります。
各業務にかかっている時間を概算し、ノンコア業務の割合が高いのであれば、最優先で改善すべきだと判断できます。
業務フローの作成 - 仕事の流れを可視化する
主要な業務について、開始から完了までの一連の流れを図式化した業務フローを作成しましょう。
誰が、どの部署から、何の情報を受け取り、どのような作業を行い、誰に、何を渡すのかを洗い出すことで、業務全体の流れと部署内外の連携が明確になります。
業務フローを作成する過程で、特定の担当者や上長で承認が滞留するボトルネックや部署間の連携不足による情報の滞留、前工程の不備による手戻りの発生、そして複数の担当者が同じような作業を行っている重複作業といった問題点が浮かび上がってくるはずです。
「ムリ・ムダ・ムラ」の特定 - 非効率の原因を探る
洗い出した業務と業務フローを基に、非効率の元凶である「ムリ・ムダ・ムラ」を探します。
トヨタ生産方式で体系化された7つのムダの視点は、具体的な問題を発見する上で非常に役立ちます。
| 加工のムダ |
必要以上の品質を目指すこと
|
| 在庫のムダ |
不要な在庫を持つこと
|
| 作りすぎのムダ |
必要以上に多く作ること
|
| 手待ちのムダ |
前工程の遅れなどにより待機すること
|
| 運搬のムダ |
不必要なモノや情報を移動させること
|
| 動作のムダ |
価値を生まない動き
|
| 不良・手直しのムダ |
ミスによる修正ややり直しが発生すること
|
上記の視点を持って部署の業務を再点検することで、「この会議は本当に必要なのか?」「この報告書の目的は何か?」といった、これまで当たり前とされてきた業務に対する根本的な疑問が浮かび上がるはずです。
【STEP2: 改善策立案】具体的なアクションプランに落とし込む
問題点が明確になったら、次は具体的な改善策を考え、実行可能なアクションプランへと落とし込んでいきます。
ECRS(イクルス)の原則で改善策を発想する
ECRS(イクルス)は、改善策を検討する上で非常に有効なフレームワークです。以下の4つの方策について、改善効果が高いとされる①から④の順番に検討していきます。
| 原則 |
何を検討するか |
具体例 |
| 1.Eliminate (排除) |
その業務自体をなくせないか?
|
目的が形骸化した定例会議や、誰も読んでいない日報を廃止する。
|
| 2.Combine (結合) |
複数の業務を一つにまとめられないか?
|
関連性の高い複数の会議を統合し、一度で報告・意思決定を行う。
|
| 3.Rearrange (交換) |
手順や担当者を入れ替えられないか?
|
承認フローを見直し、ボトルネックになっている工程の順番を変更する。
|
| 4.Simplify (簡素化) |
もっと単純・簡単にできないか?
|
報告書のフォーマットを簡略化し、ITツールでデータ入力を自動化する。
|
まずは、その業務自体をなくせるものなのか考えることから始め、それが難しければ複数の業務を一緒にこなせるか検討します。次に、業務の順序や担当者の入れ替えが可能かを考え、最後に、業務をもっと簡素化できるかどうかという視点で具体的な改善案を練り上げていきます。
業務の「やめる」「減らす」を断行する
ECRSの「E(排除)」に該当しますが、最も効果が高く、そして最も勇気が必要なのが「やめる」「減らす」という決断です。
長年の慣習で行われてきた業務をなくすことには、現場からの心理的な抵抗が伴うものです。実施にあたっては、管理職がその必要性をデータに基づいて説くことが求められます。まさに、リーダーシップの発揮しどころです。
目的の不明瞭な会議、形骸化した報告書、過剰なチェック体制などを見直すことで、時間的コストを大幅に削減できるかもしれません。
標準化とマニュアル化で属人化を防ぐ
特定の担当者にしか遂行できない属人化した業務は、業務のブラックボックス化を招き、非効率の温床となります。誰が担当しても一定の品質とスピードで業務を遂行できるよう作業手順を標準化し、誰にでも分かるマニュアル化することをおすすめします。
手順を明確化しフォーマットを統一することで新人教育が効率的になり、急な担当者変更にも、柔軟に対応可能な強い組織体制が構築できます。
ITツール導入による自動化・効率化
データ入力や定型的なレポート作成といったノンコア業務の多くは、ITツールを導入することで大幅な効率化、ひいては自動化が可能です。
近年では、比較的安価で導入しやすいクラウドサービスも数多く存在します。コミュニケーションを円滑にするチャットツールや進捗管理を可視化するタスク管理ツール、単純作業を代行させるRPA(Robotic Process Automation)などは、費用対効果の高い投資といえます。
ITツール導入の成功の鍵は目的を明確にし、まずは一部の業務から試験的に導入するスモールスタートを心掛けることです。
アウトソーシング(外部委託)の活用
経理入力やデータ入力、資料作成補助といった定型業務は、思い切って外部業者に委託するアウトソーシングも有効な戦略です。
社員は本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整い、部署全体の生産性向上に繋がります。外部業者に委託することで、自社で行うよりも高い品質とスピードを叶えられます。
目標設定(KPI)と実行計画の具体化
改善策が決まったら、ECRSを確実に実行するための計画を立てます。
計画にあたっては、「会議時間を月あたり20%削減する」「データ入力の所要時間を30%短縮する」といった、測定可能な目標(KPI: 重要業績評価指標)を設定しましょう。
目標を設定したら、誰が・いつまでに・何をするかを明確にした具体的なアクションプランを作成します。この計画が、次の実行と定着フェーズでの羅針盤になります。
【STEP3: 実行と定着】改善を文化にするためのマネジメント
どんなに優れた計画も、実行されなければ絵に描いた餅に過ぎません。そして、一度きりの改善で終わらせず、継続的に業務を見直し続ける文化として部署に根付かせるまでが管理職の役割です。
スモールスタートで成功体験を積む
最初から完璧を目指し大規模な改革に着手しようとすると、現場の抵抗が大きくなりやすく失敗したときの影響も甚大です。まずは影響範囲が小さく、効果が出やすい業務から試験的に始めましょう。
小さな成功体験は、部下の自信に繋がり、業務改善に対する前向きな姿勢を育みます。この成功事例を部署全体で共有し、次の改善活動への推進力としていくことが重要です。
部下の巻き込みと主体性の尊重
業務改善は、管理職が一方的に進めるトップダウン型では決してうまくいきません。実際に業務を行っている現場にこそ改善のヒントが隠されています。
改善策を検討する段階から現場職員を参加させ、現場の意見を積極的に吸い上げる姿勢を示しましょう。改善活動を継続するには、現場の職員の当事者意識が不可欠だからです。
定期的な進捗確認と効果測定(KPIレビュー)
計画を始動させたら、定期的に進捗状況を確認する場を設けましょう。
週に1度、あるいは月に1度のミーティングで、アクションプランが計画通りに進んでいるか、進捗状況を確認します。計画通りに進んでいない場合は、その原因を冷静に分析し軌道修正を図ります。この地道な振り返りのプロセスが、改善の精度を高めていきます。
PDCAを回し続け、継続的な改善を促す
一度改善した業務も、市場や事業の状況変化によっては再び非効率になる場合もあります。継続的な改善を組織の文化として定着させるため、PDCAを回していく必要があります。
・Plan(計画)
・Do(実行)
・Check(評価)
・Action(改善)
管理職は、PDCAサイクルを主導し、部署に定着させていく役割を担っています。例えば、STEP1・2で特定した課題に対して、以下のようなサイクルを回していくイメージです。
まず、取り掛かるのはPlanです。STEP2で立案した「定例報告書の作成時間を月10時間削減する」というKPIと、「報告書フォーマットを簡素化し、データはシステムから自動出力する」という実行計画をチームで共有します。
次は、Doです。計画に基づき、実際に新しいフォーマットを導入し、自動出力の仕組みを構築・実行します。
そしてCheckに移ります。1ヶ月後、実際の削減時間を測定し、目標との差異を確認します。同時に、職員から新たな課題をヒアリングします。
最後に、Actionとなる改善です。この評価結果に基づき、可能な改善策を検討し、次のPlanへと繋げます。目標が達成されていれば、その成功結果を横展開し、新たなサイクルを開始します。
管理職が主導してPDCAを回し続けることで、一度きりの改善で終わらせず、常に「もっと良くするには?」と模索していくことが可能となります。