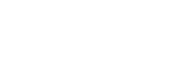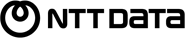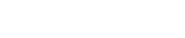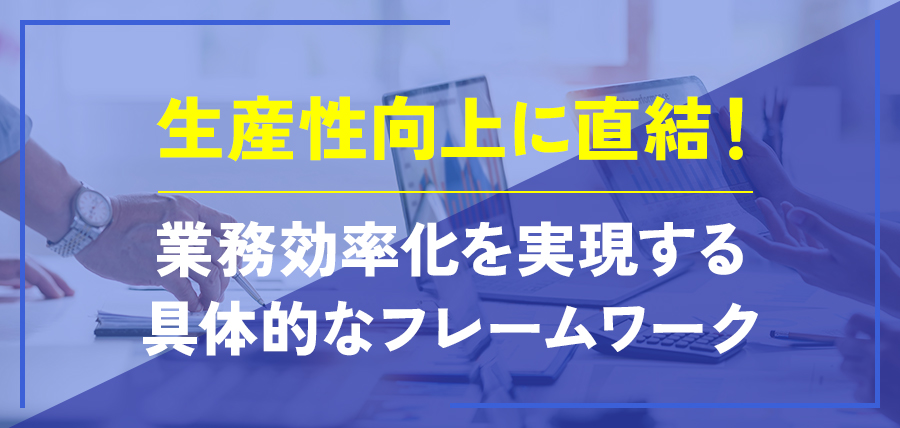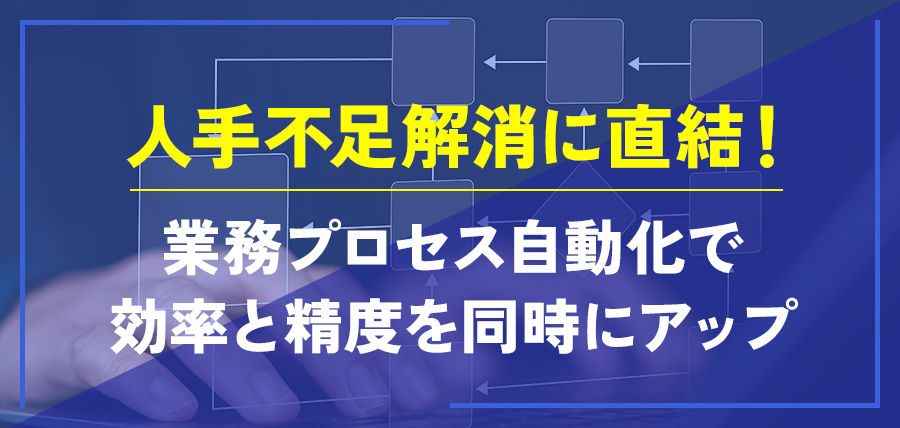01
「業務効率化」の達成だけでは不十分?その先の「生産性向上」が重要な理由

まずは、業務効率化と生産性向上の違いを明確にし、生産性向上がなぜ中小企業にとって重要なのかをみていきましょう。
業務効率化
主に時間・労力・コストなどのインプットを削減することに焦点を当てます。例えば、会議時間の短縮やRPAによる手作業の自動化などがこれに該当します。目的は、「ムダをなくすこと」であり、生産性向上のための重要なステップです。
生産性向上
より少ないインプットで、より大きな成果・付加価値であるアウトプットを生み出すことを目指します。生産性向上とは、インプットを維持しつつアウトプットの量や質を高める状態、もしくは、効率化で削減した少ないインプットで従来と同等以上にアウトプットする状態です。目的は、成果を最大化することです。
では、効率化で終わらず、生産性向上を目指すことがなぜ不可欠なのでしょうか。その理由をひとつずつ確認していきます。
1.リソースの制約と成長機会の創出
経営資源が限られる中小企業にとって、少ないリソースで最大の成果を上げることは経営戦略上の最重要課題です。但し、効率化でリソースの浪費を抑えただけでは、現状維持に留まる可能性があります。生産性向上によって生み出された余力を、新商品開発、新規市場開拓、従業員教育といった未来への投資に振り向けることで、企業は成長軌道に乗れます。
例えば、月間10時間の余力が生まれたら、市場調査や顧客ヒアリング、新たなニーズを発掘などの行動に時間があてられます。
2.利益構造の抜本的改善と持続的成長
生産性が向上すると、同じコストでより多くの製品やサービスを提供できると同時に、高付加価値を提供でき、利益率の改善に直結します。生産性の向上は、単にコストカットするよりも強力な利益改善となります。得られた利益は、さらなる事業投資や環境変動・不測の事態への備えとなり、持続的な成長を支える協力な財務基盤を築きます。
例えば、食品製造企業で不良品率が半減すれば、材料費や再生産コストが削減され、利益が直接的に増加します。
3.競争力強化と市場での差別化
物事の不確実性が高く、将来の予想が困難な状況である、いわゆるVUCA時代の市場において、競合と差別化し、優位性を確立するためには、常に新しい価値を提供し続けなければなりません。生産性向上によって生み出されたリソースを、新技術導入、ビジネスモデル変革、顧客体験の向上などのイノベーティブな活動に投下することで、競争力を強化できます。
例えば、AIを活用した新サービス開発にリソースを集中させ独自の価値を提供する、といった戦略が可能です。
イノベーティブな活動により価格競争からの脱却も狙えます。
4.従業員満足度(ES)向上と人材確保
「ムダな作業が減り、より創造的で価値の高い仕事に集中できる」「自分の成長が会社の成長に貢献している」という実感は、従業員のモチベーションやエンゲージメントを高めます。また、労働環境の改善やキャリアアップにもつながるため、結果として優秀な人材の獲得・定着が進み、採用競争力強化にも繋がります。人手不足が深刻化する中小企業にとって重要な意味を持つといえるでしょう。