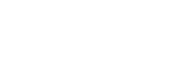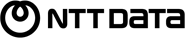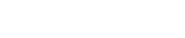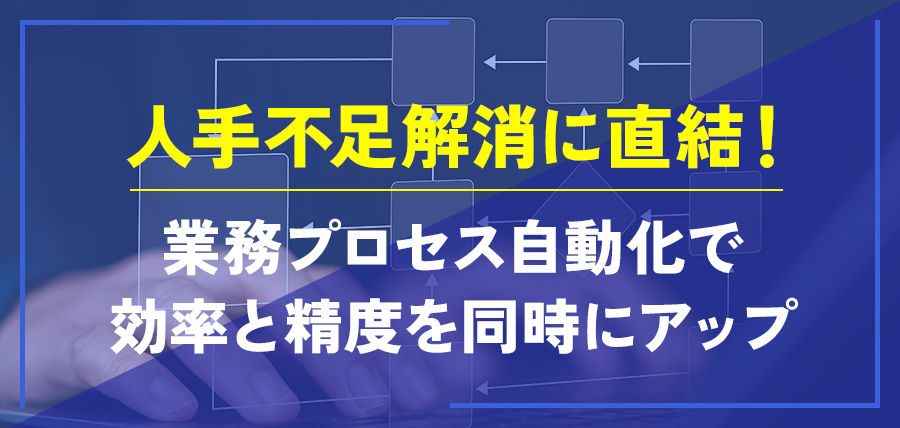01
RFM分析とは「3つの指標」で顧客の現況を把握する分析手法

RFM分析は、顧客の購買データから「どの顧客が自社にとって重要か」を定量的に評価します。
RFM分析とは
RFM分析は、顧客の購買行動を表す「最終購入日(Recency)」「購入頻度(Frequency)」「累計購入金額(Monetary)」という3つの指標で顧客をグループ分けする分析手法です。
これら3つの指標の頭文字から、RFMと略して呼ばれています。
単に、売上金額だけで顧客を評価するのではなく、直近の購入日や購入頻度まで分析することで、顧客のニーズに合わせたセグメンテーションが可能となり、顧客満足度とLTVを高めるメリットがあります。
R (Recency):最終購入日
Recency(最終購入日)は、顧客が最後にいつ購入したかを示す指標です。最終購入日からの経過時間が短い顧客ほど高く評価されます。
例えば、直近30日以内に購入があった顧客は、今後も継続的に購入してくれる見込みが高いと考えられます。一方、最終購入日が180日以上前の顧客は、既に他社に乗り換えているか、そもそものニーズが変化している可能性があります。このような顧客には、通常のマーケティング施策よりも「呼び戻し」に特化したアプローチが必要となります。
尚、業種によって「最近」の基準は大きく異なります。日用品のような消耗品を扱う企業では30日、家電のような耐久財を扱う企業では1年から数年といった具合に、自社の商品特性に応じて適切な基準を設定することが重要です。
F (Frequency):購入頻度
Frequency(購入頻度)は、一定期間内に顧客が何回購入したかを示す指標です。購入回数の多い顧客ほどスコアは高くなります。
継続的に商品を選んでくれるということは、品質やサービスに満足している証拠であり、今後も安定した売上貢献が期待できる重要な顧客層です。
そのため、新商品の案内や関連商品の提案に対しても反応が良く、クロスセルやアップセルの成功確率が高いという特徴があります。一方、購入頻度が低い顧客に対しては、まず、購買習慣の定着を促す施策が必要となります。
M (Monetary):累計購入金額
Monetary(累計購入金額)は、一定期間内に顧客が購入した金額の合計を示す指標です。累計購入金額の高い顧客ほどスコアが高くなります。
この指標は、顧客の売上への直接的な貢献度を表しており、企業にとって、特に価値の高い顧客を特定するために不可欠です。例えば、顧客単価が1万円であれば、直近1年間で10万円以上の購入実績がある顧客は、明らかに自社の重要顧客として位置づけるべきでしょう。
但し、Monetary単体では顧客の全体像は見えません。例えば、過去に一度だけ高額商品を購入した顧客と、継続的に商品を購入し続けて結果的に高額になった顧客では、今後の購買可能性は大きく異なります。
RとFの指標と組み合わせて評価することで、売上も購入頻度も高い「優良顧客」と、「過去に大量に購入してくれたものの、現在は購買していない休眠顧客」を把握し、それぞれに適した施策を検討できます。