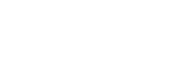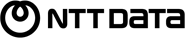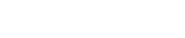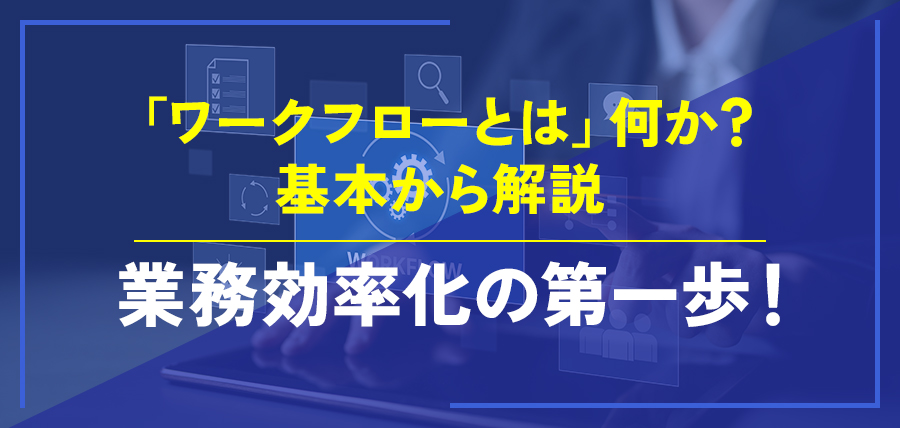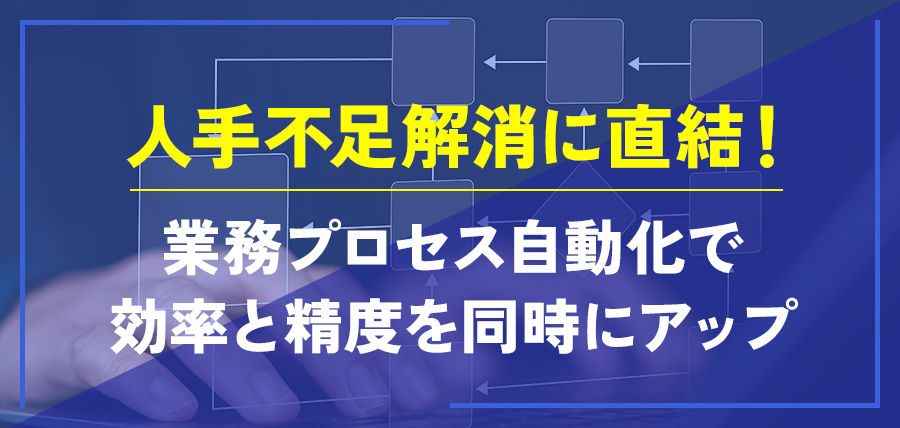03
ワークフローを見直す・システム化するメリット~効率化だけじゃない価値~
ワークフローを見直しシステム導入することで、中小企業は多くのメリットを享受し、業務効率化を加速できます。ここでは、ワークフローの見直しやシステム化を行う6つのメリットをご紹介します。
メリット1:圧倒的な業務効率化(時間短縮・手間削減)
申請書の作成から承認までのプロセスが、デジタルで完結することで、決裁までの時間が大幅に短縮されます。
自動通知やリマインダー機能で承認の遅れを防ぎ、モバイル対応により、場所を問わず業務を進められるため、担当者はより重要な業務に集中できるようになるでしょう。
メリット2:ミスの削減と内部統制の強化(承認漏れ防止、証跡管理)
入力内容のチェック機能やあらかじめ設定された承認ルートにより、申請書類の記載ミスや入力漏れを防ぎ、手戻りの削減に貢献します。承認履歴はすべて自動で記録されるため、後から確認や監査がしやすくなり、不正防止や監査対応が容易になります。
これにより、企業のコンプライアンス強化が可能です。
メリット3:進捗状況のリアルタイム可視化と意思決定の迅速化
各業務プロセスの進捗状況が、リアルタイムで可視化されるため、申請が「今、誰のところで止まっているのか」といったボトルネックを一目で把握できます。
これにより、問題点を早期に特定し、業務プロセスの改善を促進し、組織全体の生産性向上も実現できるでしょう。
メリット4:ペーパーレス化によるコスト削減と情報共有の促進
紙の申請書が不要になることで、印刷代、用紙代、郵送費などの直接的なコストを削減できることもメリットのひとつです。
書類の保管スペースや管理にかかる人件費も削減でき、情報管理のセキュリティも向上します。
メリット5:属人化の解消と業務標準化
ワークフローをシステムに落とし込むことで、特定の人にしかわからない属人業務を減らすことが可能です。
業務プロセスが標準化され、担当者が変わってもスムーズに引き継げるため、業務の安定性が向上します。
メリット6:テレワークなど多様な働き方への対応基盤
クラウド型のワークフローシステムは、インターネット環境があれば場所を問わず申請・承認が可能であり、リモートワークや出張時でも業務が滞りません。
これにより、押印のためだけに出社する必要がなくなり、従業員の柔軟な働き方を実現できます。